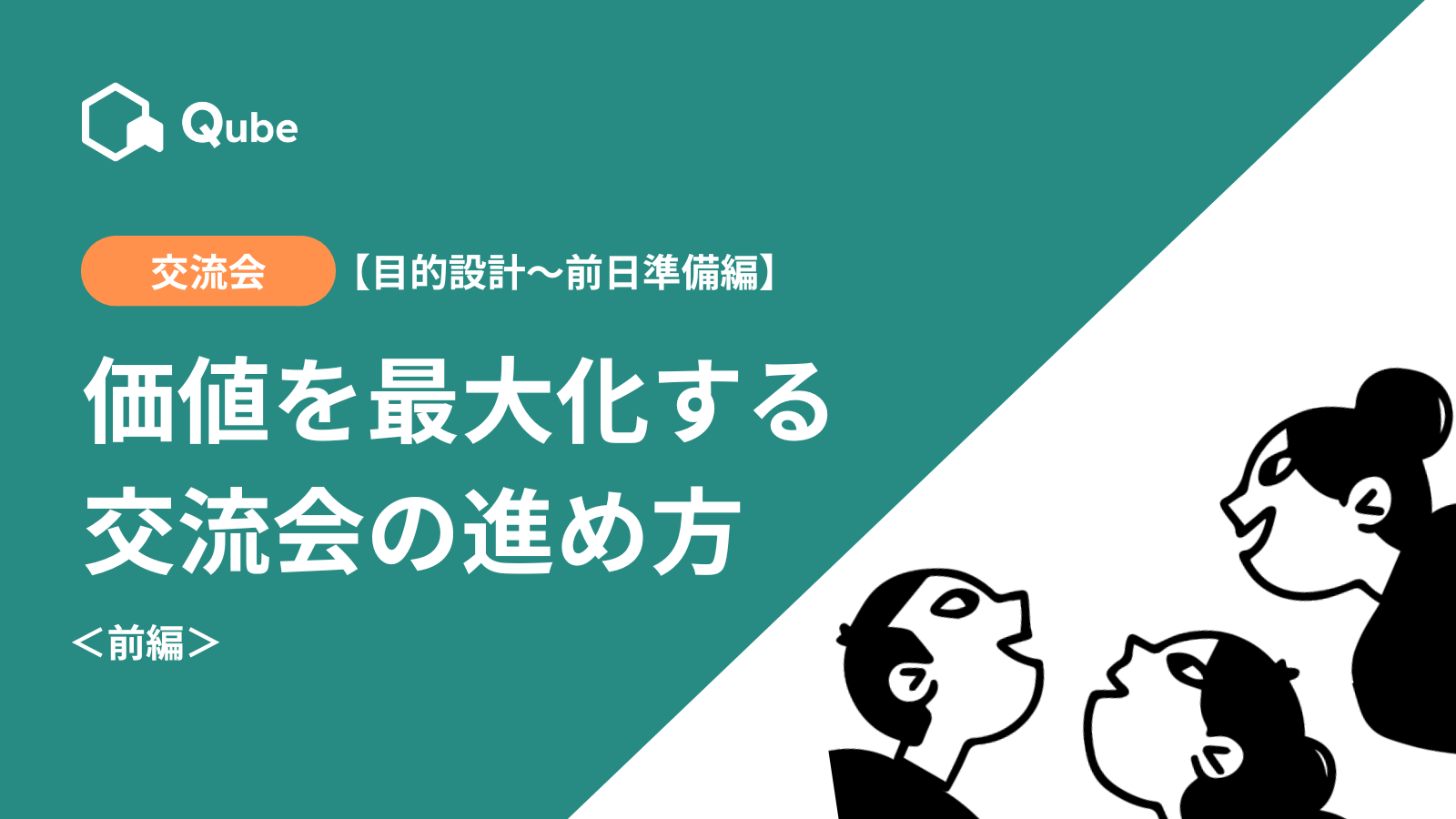「交流会ってどうやって進めるのが正解なんだろう?」
「なんとなく自己流でやってきたけど、これで合ってるのかな?」
そんなふうに感じたことはありませんか?
この記事では、株式会社シー・エス・エスが実際に行っている交流会の進め方を、成功例・失敗例とあわせてご紹介します。
今回は前編・後編の2部構成でお届けします。
前編では「目的設計~前日準備」までの交流会の進め方を、後編では「当日運営~アフターフォロー」までの流れを詳しく解説します。
これから交流会を開催したい方はもちろん、何度か経験があるけれど「これでいいのか不安…」という方にも参考になる内容です。
私たちの実践例が、あなたの交流会をもっと良くするヒントになればうれしいです。
後編が気になる方はこちらからどうぞ
coming soon
目的設計:成功する交流会は「目的の明確化」から始まる

交流会の企画で最初にやるべきことは、「なぜ開催するのか?」という目的を明確にすることです。目的が曖昧なままだと、交流会の進め方そのものがブレてしまい、内容や集客の軸も定まりません。
例えば、弊社では以下のような目的を持って交流会を開催してきました。- IT企業や経営者に特化したビジネス交流の場をつくる
- 異業種の方々が交わる新しい出会いの場をつくる
- 他社とコラボしたユーモアある交流会(例:卓球大会付き交流会)を実施する
目的が明確であれば、ターゲットやテーマ、演出まで一貫した設計が可能になり、交流会の進め方も自ずと見えてきます。さらに、参加者にどんな価値を持ち帰ってもらうのかまで設計できていれば、満足度の高い交流会を実現できます。
ターゲット設計:交流会の質は参加者のバランスで決まる

交流会の進め方を考える上で、参加者の属性設計は極めて重要です。
どれだけ企画や会場にこだわっても、集まる人がズレていると満足度は一気に下がってしまいます。
「目的」によって、どんな人を集めるべきか決める
「IT業界の企業同士の連携を促進したい」という目的なら、その領域に関わる人が交流会でのターゲットになり、「異業種交流を促す場」であれば、あえて属性を広げて様々な方に来てもらう必要があります。
弊社でも、こうしたターゲット設計に成功したことで高い満足度を得られた一方、目的とターゲットがズレたことで苦戦した失敗例もあります。
例えば、過去のビジネスマッチングの交流会で「芸能人を招いて、楽しい雰囲気の交流会を演出すれば集客しやすいのではと考え企画したことがありました。
ところが、実際に集まったのは「ビジネス目的で名刺交換や仕事につながる出会いを求めている方々」が中心。
参加者の多くは、交流会では笑いやエンタメよりも「実利的な出会い」を重視していたため、コンセプトとニーズが合わず、集客も想定より伸びませんでした。
また、男女比にも配慮しています。男性が多くなりがちなビジネス交流会だからこそ、女性の集客にも力を入れるなどして、偏りのない構成を心がけています。
来てほしくない参加者を明確にする
そしてもう1つ大切なのが、交流会で「来てほしくない人」を明確にすることです。どんなに良い交流会でも、目的にそぐわない参加者がいるだけで、場の空気は一気に崩れます
- 保険や投資商品の売り込みを目的とした営業マン
- マルチ商法(MLM)やネットワークビジネス関係者
- 勧誘行為が目的の人
- 交流ではなく営業だけをしに来ている人
- 異性との出会いなど、ビジネスと関係ない目的の人
弊社では、こうした属性の人の参加を防ぐために、事前アンケートや申し込み管理機能を活用し、属性を把握した上で案内やリマインドを調整しています。これにより、安心感と信頼性のある交流会づくりが可能になっています。
企画設計:差別化される交流会をつくる

交流会の目的とターゲットが明確になったら、次は「どんなイベントを企画するか」がカギになります。
数あるイベントの中から自分たちの交流会を選んでもらうためには、「参加する理由」があるイベントにしなければなりません。
成功事例のご紹介
弊社の交流会では、ただのビジネスマッチングではなく、「この交流会は他とはちょっと違う」と思ってもらえるような企画づくりを心がけています。
- 会場へのこだわり
麻布台ヒルズや渋谷のバーなど、雰囲気のある空間を厳選して開催。 - おいしい料理の提供
イベント内容にあった素敵なケータリングを注文し、品切れの心配がないよう配慮。 - 細部まで行き届いた演出
音楽・照明・ノベルティまで、空間を彩る要素を徹底的に演出。 - ユーモアのある企画
他社とのコラボや卓球大会など、思わず笑顔になる遊び心をプラス。
実際に、「料理がすごく美味しかった」「雰囲気が良くてリラックスできた」という声を多くいただいており、これが次の集客にもつながっています。
外資系のIT企業のイベントに参加した際、「おしゃれな雰囲気を演出するBGM」や「体験や出会いを重視している点」など、気づいたポイントをそのまま自社の企画に活かしています。常に新しい刺激を取り込むことで、独自の価値を磨いてきました。
集客戦略:集客で失敗しないためのポイント

交流会を開催する中で、最も多くの主催者が苦戦するのが「集客」です。
弊社でも、最初は「広告を出せば来るだろう」と安易に考えたことがありました。ですが実際はなかなか反応が得られず、集客には「設計」と「工夫」が必要だと痛感しました。
ハウスリストを活用したメルマガ戦略
弊社が現在、最も安定的に活用しているのがハウスリストへのメール配信です。
特にメルマガは、うまく活用すればコストをかけずに高い反応を得ることができます。
多いときは1週間に2〜3回のペースで配信し、開封率20%以上を目指しています。そのために意識しているのが「開封される件名(タイトル)」です。
- 「〇月〇日開催|〇〇限定交流会」など、一目で内容がわかる日付入りタイトル
- 「〇〇様、ご都合いかがでしょうか?」など、名前を呼びかけるようなパーソナルな文面
- 「先着◯名様」「〇〇限定」など、希少性や限定感を伝える工夫
- 「コスト削減!」などの参加した時のベネフィットを見せる
こうした配信を積み重ねることで、「参加します」「興味あります」といった反応が着実に増えていきます。
集客に“強い”プラットフォーム選びも重要
また、弊社ではQubeというBtoBイベント特化型のプラットフォームも活用しています。
Qubeは、
- イベント掲載が無料
- 手数料は3%(掲載は無料)
- 2800社のBtoB企業に直接リーチできる
- SNS機能やアンケート機能で属性管理もできる
- 申し込み後のフォローや連絡が一元管理できる
といった特徴があり、集客の効率と管理の手間を大幅に軽減してくれます。
実際に弊社でも、Qubeを活用することで一元管理ができ、集客に専念することができました。また、Qube内案内からも申し込みが入っており、集客媒体としても活用しております。
事前準備:交流会の進行を左右する事前段取り

当日の進行がスムーズにいかなければ、全体の印象は一気に下がってしまいます。
特に交流会のように多くの人が一斉に動く場では、細かい準備と段取りが不可欠です。
前日のチェックが「もたつき防止」のカギ
交流会当日のバタつきやトラブルを防ぐために、大切にしているのは、「段取りの可視化」と「細部の詰め」です。
現場では、一つの手配漏れが混乱につながることも少なくありません。
だからこそ、“誰が・いつ・何をやるか”をあらかじめ明確にし、全員が共有しておくことを徹底しています。
例えば
- 受付スタッフの人数・配置・導線を図で設計し、混雑や滞留を回避
- 名札、配布物、釣銭、筆記具などの備品をすべてリスト化し、前日中にチェック
- 想定質問やクレーム対応のシナリオを事前に用意し、スタッフ間でロールプレイング
準備の段階で、「いつ」「どのタイミングで」何が必要かを細かく可視化しておくことが、当日の余裕と参加者への安心感につながります。
交流会準備チェックリスト参考例
【受付準備】
- 受付担当者の人数と配置が決まっている
- 受付の机・椅子・筆記用具を準備している
- 混雑回避のため、受付の動線を確認している
【備品・資料関係】
- 配布資料・パンフレット・アンケートを印刷している
- 名刺回収ボックスやチラシ設置スペースを用意している
- サイン台・テーブル番号札・案内板などの備品が揃っている
- ノベルティや料理をリスト化している
【会場・レイアウト】
- 会場のレイアウト図を作成・共有している
- 音響・照明・マイク・プロジェクターなどの機材をチェックしている
- 電源やWi-Fiの使用状況を確認している
- 会場内外の導線と案内掲示を設計している
【運営体制】
- スタッフ全員に当日のスケジュール・役割を共有している
- 開場〜閉場までのタイムラインを設定している
- トラブル時の対応フロー(連絡先含む)を確認している
- 荷物の搬入・搬出方法を確認している
【参加者対応】
- Qubeなどのツールで参加者情報を最新にしている
- 属性や業種に応じたグループ分け・紹介文を整理している
- 参加者向けに事前リマインドメールを送信している
- アンケートやフォロー用の連絡先を事前に準備している
このようなチェックリストがあることで、当日焦ることなく、主催者として自信を持って交流会に臨むことができます。
おわりに|準備が整ったら、次はいよいよ本番当日!

ここまで、企画から集客までの交流会の進め方について、弊社の実例を交えながらご紹介してきました。
初めての開催でも、何度目かの開催でも、「本当にこのやり方でいいのか?」と迷う瞬間は必ずあります。
だからこそ、目的を定め、ターゲットを明確にし、企画を差別化し、準備と集客を丁寧に積み重ねていくことが、成功への1番の近道です。
本記事でご紹介した内容が、皆さんの交流会に少しでも役立てば幸いです。
後編では…
次回の【後編】では、「当日運営~アフターフォロー編」までの進め方をさらに詳しくお届けします。
交流会をよりスムーズかつ効果的に進めるための、実践的なノウハウが満載です。
-
受付で「もたつきゼロ」にする導線設計の秘密
-
初対面でも会話が始まる方法とは
-
進行の遅れを感じさせないタイムラインの作り方
-
終了直後に次回参加意欲を高めるためにやること
-
Qubeで運営からフォローまで完結させる方法
準備が整ったら、次はいよいよ本番当日!
続きはこちらからどうぞ
coming soon