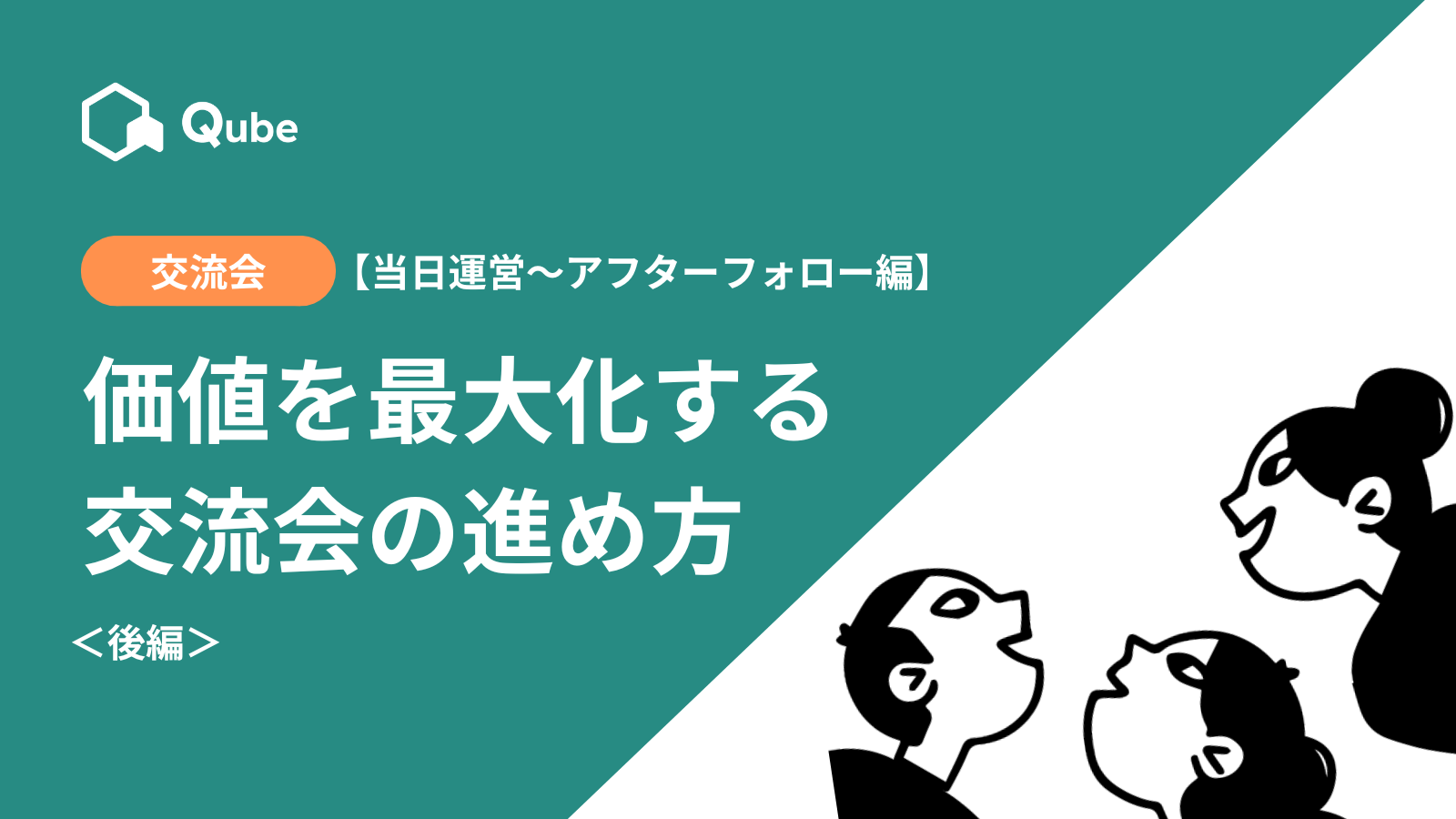前編では、交流会の企画・ターゲット設定・集客の話を中心にお伝えしましたが、後編では、いよいよ当日の運営〜アフターフォローまで、実際の運営フローを深掘りしていきます。
ここからご紹介する内容は、弊社が3年以上毎月100人規模の交流会を開催して得た、リアルな経験と改善の積み重ねです。
「交流会前日になって慌てる…」というようなことが起こらないよう、細かいポイントも含めてお伝えしていきます。
当日の運営:もたつきを防ぐ

交流会で最初に訪れるのが「受付」です。
ここでスムーズに案内されるかどうかで、その後の参加者の心理的ハードルが変わります。
弊社では導線から開場時まで意識しているポイントがあります。
【導線の工夫】
- 受付から会場までの動線を、貼り紙と口頭で案内
- トイレ・クローク・喫煙所などの案内も明確に
- 入場後の動きがスムーズになるように、入口付近での人の滞留を減らすレイアウトにする
【開場時に意識していること】
- 交流会の内容に応じて、音楽・照明・会場レイアウトで空気をつくる
- 交流会が始まる前に、軽いアイスブレイクになる仕掛け(ウェルカムドリンク・名刺交換タイムなど)を用意
- 1人参加の方が孤立しないように、スタッフが自然な声かけを行う
導線と開場設計は、「はじめての参加者でも安心できる」ことが最優先です。
第一印象がよければ、それだけで交流会の空気は柔らかくなり、交流も生まれやすくなります。
当日の進行管理:流れを崩さず、柔軟に運営するコツ

受付が落ち着いたら、いよいよ本番のスタートです。
ここで重要なのは、決めたスケジュールを守りつつ、柔軟に運営する力です。
予定通りに進めることは大切ですが、実際の現場では予定通りにならないことも多く起こります。そのズレにどう対応するかが、主催者としての腕の見せどころです。
タイムラインは余白をもって組む
弊社では、交流会やセミナーのタイムスケジュールを作る際に、以下のような余白を意識しています。
- 全体を通して「5〜10分」のバッファーを設ける
- トラブル時の巻き返しができるよう、司会進行役に柔軟な調整権限を持たせる
- セミナー付き交流会などでは「質疑応答時間の延長ありき」で設計する
- セミナーや講演の場合はタイムキーパーが時間を管理する
その結果、たとえ進行が押しても参加者にバタバタ感を与えず、落ち着いて進行できるようになります。
スタッフの配置は「空気を読む役割」も含めて設計
交流会の運営を成功させるためには、進行役だけでなく場を整えるスタッフの存在も必要です。
例えば、
- 名刺交換がスムーズに行われていないテーブルに、スタッフがそっとフォローに入る
- 会話に入りづらそうな方を、さりげなく別のグループに誘導する
- 長時間立ちっぱなしの参加者がいれば、ドリンク案内をする
こうした気配りが、「この交流会、質が高いな」と感じてもらえる要素になります。
トラブル時の対応フローも決めておく
過去には、以下のようなトラブルがありました。
- 参加者が開始時間に遅れて会場がわからず混乱
- 会場備品が手違いで準備されていなかった
- 外部ゲストの到着が遅れ、プログラムにズレが生じた
- 参加の申し込みをしてない方が来場した
弊社ではスタッフを多めに配置しておくことでこういったトラブルを回避してきました。
とはいえ、どれだけ準備していてもトラブルはつきものです。
大切なのは、事前に判断基準や連絡ルートを共有しておくことです。
さらに、開催を重ねるごとに改善点を見つけていく姿勢が、運営の質を高めていきます。
アフターフォロー:イベント後の動きについて

お礼と次回予告をする
交流会終了後は、できるだけ早くお礼の連絡を送りましょう。
参加への感謝とともに、「今後の交流会開催予定」や「次回の交流会兼セミナーの案内」をさりげなく盛り込むことで、参加者の中に自然と次も行ってみようかなという意識を育てることができます。
文面は形式的になりすぎず、当日の空気感を思い出せるようなトーンで、参加者の記憶が鮮明なうちにアプローチすることがポイントです。
アンケートで参加者の声を拾い、関係を深める
交流会後のアンケートは、運営改善の材料であると同時に、参加者との信頼関係を築くきっかけにもなります。
満足度だけでなく「次に参加したいテーマ」や「印象に残ったこと」などを聞くことで、次回の企画精度が高まるだけでなく、「自分の声が反映される交流会なんだ」と感じてもらえます。
アンケートはなるべくシンプルに、スマホで完結する形がおすすめです。
SNS発信でイベントの余韻と認知を広げる
弊社では、開催後に交流会の様子をSNSで発信しています。
参加者の写真や会場の雰囲気、印象的なシーンなどを投稿することで、交流会の空気感が可視化され、認知拡大にもつながります。投稿に参加者がリアクションしてくれれば、自然な形で話題が広がり「この交流会に自分も参加してみたい」と感じる新たな層へのアプローチにもなります。
SNSは交流会の延長線として活用することで、参加者とのつながりを保ちつつ、まだ参加したことのない人に対しても「雰囲気がよさそう」「こんな人たちが来ているんだ」といった安心感や期待感を提供できます。
無理に拡散を狙うのではなく、「来てよかった」「また行きたい」と思える余韻を共有する場として設計することがポイントです。
Qubeで完結する運営とフォローの仕組み化

交流会の運営では、集客、受付、フォローアップと、さまざまな工程を並行して行う必要があります。これらをすべて手作業で行っていると、どうしても漏れやミスが生まれやすくなります。
弊社ではそれらを一元管理できるツールとして、BtoB向けプラットフォーム「Qube」を活用しています。
Qubeでは以下のことができます。
- イベントの無料掲載が可能で、見込み顧客に広くアプローチ
- 参加申し込み時に事前アンケートを設定でき、参加者属性を可視化
- 参加者へのリマインドメールや事前案内を一括送信
- 受付リストや当日確認もQube上で完結し、チェックインがスムーズ
開催後のアンケート配信やSNS連携など、フォローアップが可能です。
Qubeの活用例
弊社では、イベントの掲載から申込受付、当日の運営、終了後のサンクスメールの送付まで、すべてQube上で完結しています。これにより、主催者側の手間やミスを最小限に抑えつつ、参加者にもスムーズでストレスのない体験を提供できています。
例えば「決裁者限定交流会」の企画では、申し込みフォームに役職や会社規模を入力してもらうことで、参加条件に合致するかを事前に確認できます。
事前アンケートの結果をもとに、参加者同士のマッチングや当日の席配置を最適化しています。あわせて、集客経路ごとの効果を可視化し、成果の高い媒体やチャネルに重点を置くことで、交流の質と集客効率の両面で改善を図っています。
このプロセスによりイベントの質を担保しながら信頼感のある運営が可能となり、参加者からも「安心して交流できた」という声を多くいただいています。
BtoBコミュニケーションプラットフォーム「Qube」の紹介

特にBtoBの異業種交流会やセミナーの集客、イベントのサポートとして優秀な「Qube」をご紹介します。
Qubeは現在2800社以上の企業が登録(2025年8月現在)しており、企業同士がビジネスの相談や情報交換、マッチングを行えるコミュニケーションプラットフォームです。企業の担当者がビジネス目的で利用していることが大きな特徴です。
イベントを主催するための機能が豊富なQube
Qubeが交流会・セミナーを主催するために必要な機能がたくさんあり、Qubeを活用する理由は4つあります。
- BtoB企業が集まる場所:
2800社以上の企業が登録しており、ビジネス上の課題解決やネットワーキングに関心を持つ企業の担当者に直接リーチしやすい環境です。 - 基本利用料が無料:
イベント申込ページの掲載は無料です。
※参加者向けの決済機能を利用した場合は、決済手数料が約5%掛かります。 - 充実している多数の機能:
イベント申込時の事前アンケートやSNS投稿機能による発信など、機能が豊富にあります。 - Qube会員へのメール通知:
イベントの開催情報を、各イベント毎に3回まで無料で全てのQube会員にメールで通知することができます。配信の日付指定と時間指定も可能です。
これらの機能を活用すれば、初めての主催でも「集客・運営・フォロー」が無理なく実現できます。
交流会・セミナー運営をもっとスムーズに、もっと成果につなげたいと考えている方は、ぜひ一度Qubeを活用してみてください。
登録は無料、所要時間はわずか3分です。
あなたの交流会を、Qubeがしっかりサポートしてくれます。
まずはイベントを掲載するところから、はじめてみませんか?
▽Qubeへの登録はこちら▽
https://www.css-net.co.jp/qube
まとめ
交流会は「企画して終わり」ではありません。
開催前の準備、当日の運営、そして終了後のフォローアップまで含めて、ようやくひとつの成功がつくられます。
今回ご紹介したポイントは、私たち自身が試行錯誤を重ねながら辿りついた、実践的なノウハウです。あくまで一例ではありますが、皆さんのイベントにも活かせるヒントがあれば嬉しく思います。
そして、この一連の流れを無理なく・スマートに実現するためのツールとして、Qubeは非常に有効です。
イベント掲載、受付、アンケート、SNS連携まで一元管理できるからこそ、主催者は本来の目的に集中できます。
ぜひ、皆さんの次の交流会運営にQubeを活用してみてください。